こんにちは!
Takatoraです。
今回は民法についてです。
専門試験全般については、こちらを参照
1、民法の知識は仕事で役に立つ

私は直接法務部局で働いたことがありません。
しかし、民法の知識は仕事で役に立つケースがあります。
例えば、法人指導を行う部局へ配属になった場合は法人が私人に対して行った行為を、民法に当てはめて検討し、違法に当たる場合は指導を行ったりします。指導業務は都道府県庁の中でそれなりの部局を行っています。
公務員にとって民法は分かってて当然の知識です。ですから、試験に受かる以上に晴れて公務員になった時困らないために勉強してください。
2、民法の出題頻度
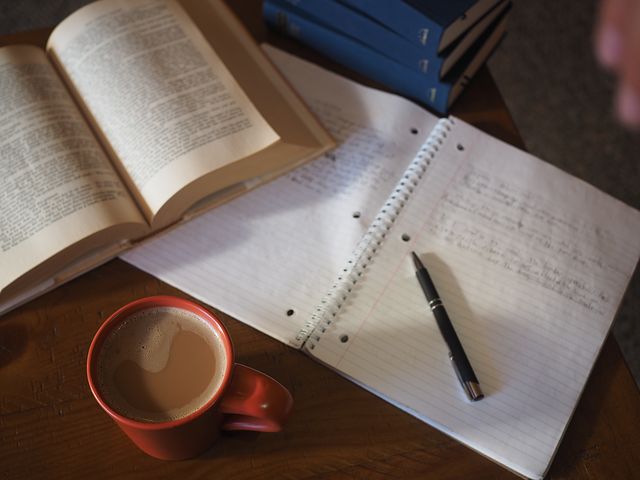
ほとんどの公務員試験で民法は必須科目となります。
国税専門官ではなんと8問も出ます!仕事柄企業の指導が専門ですから、この量は当たり前かもしれません。
その他、都庁では専門記述試験で出題されます。専門記述問題は「分かっている」だけでは正答できず、「教えられる」境地にまでいっていないと満点をもらえません。この差ってとてつもなく大きいんです。
また、択一試験も「文章理解か?」と思うくらい長文の問題があったりします。
そういうことで、民法は公務員にとって必須の科目なのです。
3、民法はイメージ

ただ必須と言ったって、分量も多いし難易度高い問題もバンバン出るし、民法なんてそんな簡単に覚えらんないよ!ってなりますよね。
私も量が多すぎてかなりヤケクソ状態で勉強していました笑
きちんと理解しないままドンドン問題集を回しましたが、単に回すだけでは全然頭に残らず「こりゃダメかも」と危機感すら感じました。
そうして、知識が定着しないままやっていく中で、少しの発見がありました。
それは、一定量の知識そのままを一かたまりに図にする事が出来るという事です。
一かたまりに出来るって結構いい事なんです。例えば、所有者と賃借人と転貸人と関係です。お互いに関係しあっているので、それぞれの立場でまとめた図を作ることができるんです。
同じように、表見代理なんかも三者の関係性から図を作ることができます。実際の問題はその図のどういう場面なのか当てはめればあっという間に解くことができます。
問題集を回す際、作った図を見ながら解くと理解スピードがあがります。そして徐々に図を頭の中でイメージする方向にシフトしていくのです。
このイメージ法、民法が苦手な人は試しに使ってみてください。